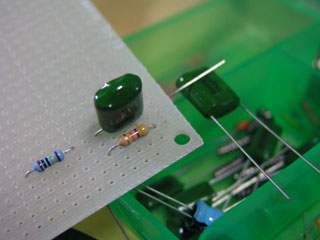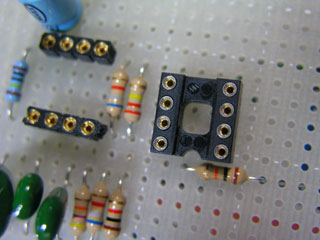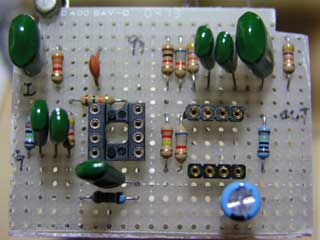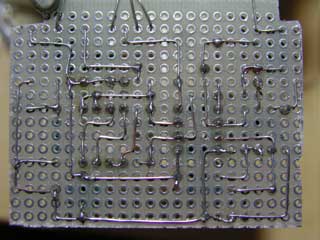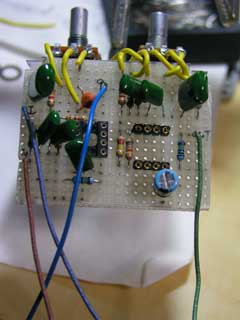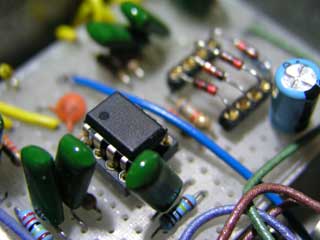|
ネット上にはかなりの数にのぼる「回路図」やら
「実体配線図」がアップされているようです。
そこで今回は「教科書」から少し離れ
「F-DRIVE」とは性格の異なった
オーバードライブに挑戦したいと思います。
これまで学んだことを念頭に置き
1.高域を増強しブースターとしても使える。
2.ギター側のヴォリュームを下げた
クリーンサウンドを好みの音にする。
を目指したいと思っています。
|
 |
ググルとホントに沢山の回路図がヒットしました。
これだけ多いと非常に迷います。
しかし、最後は直感で選び製作開始です。
以前、掲示板に書き込んでくださった
「半田ヲタク」さんのアドバイスに従い
一つ一つのパーツを800番の
紙やすりで磨きます。
|
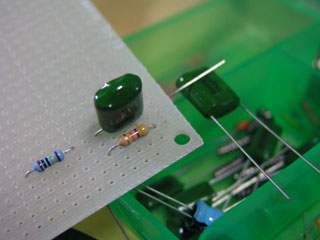 |
そして挿しては曲げてハンダ付けの開始です。
|
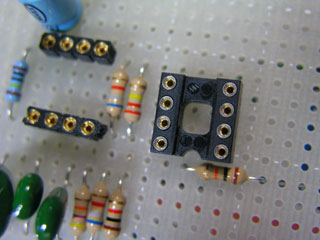 |
やはり、保険の意味も兼ねオペアンプと
クリッピングダイオードはソケットにしておきます。
|
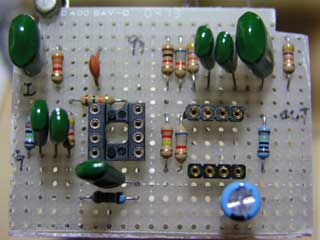 |
で、こんな感じになりました。
詳しい方ならどこのサイトの何を参考にしたか
一発で分かるんでしょうねぇ・・・
|
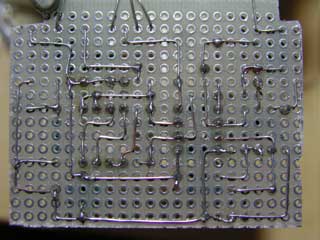 |
裏側です。
なるべく必要最低限の半田使用を
心がけたつもりなのですが・・・
|
 |
で、「小さい方」のケースに
収めるつもりだったのですが、
若干基盤が大きく無理でした。
そこで、両端をヤスリ掛けしなんとか収容。
相変わらずの
スラップスティックビルドであります。 |
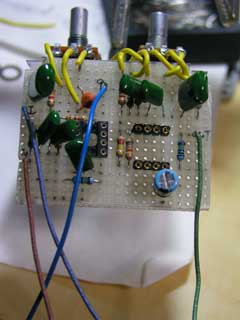 |
そして、基盤から伸びる線材を装着し
|
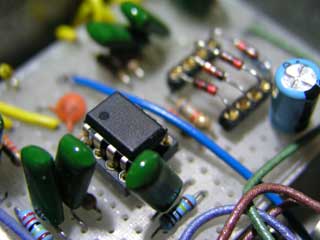 |
内部配線を済ませオペアンプと
クリッピングダイオードをソケットに挿し
電池を入れケーブルを挿しこみ
スイッチ |
 |
オン
LEDは点灯しました。
しかし「エフェクターを創ってみたよ」としては
不測の事態が・・・
一発で音も出ちゃいました。
多少は成長したと思いたいのですが・・・
しかし、ここからが試行錯誤の始まりな訳でして・・・今までのように「教科書」という名の
「ここのパーツを換えると〜になる」と記してある
羅針盤が無い訳ですから、比較用の音源を
作成する余裕の無いほど執り付かれた様に
パーツの付け替えを行いました。
そして
|
 |
一区切りの頃合と判断し
サンプル音源アップしてみることにします。
音源の 前半はストラトキャスターのリアPU
後半はフロントPUです。(以下共通)
EF OFF SOUND(140kbMP3)
VolumeFull Tone0 DriveMiddle Sound
(170kbMP3)
VolumeFull Tone0 DriveFull Sound
(207kbMP3)
まぁ、こんな感じです。
Tone0に注目してください。
高域はこれを基準にしギター側の
トーンコントロールで微調整するという
健全な発想から、こうしてみました。
もちろん高域が足りない時にはエフェクター側のToneを上げれば良いわけですからね。 |
 |
次はフロントPUとセンターPUミックスで
ギター側のヴォリュームコントロールを下げた
音のサンプルです。
前半が10で後半は4まで下げてます。
GuitarVo.10&4 Sound(155kbMP3)
ヴォリューム操作だけでこれくらい変化が
つけられると、かなり使いやすいと
思いませんか?
羅針盤無しでしたが、だいぶ目標としていた
音に近づいてきました。
が
更に実験してみたい事がありますので
続行! |
 |
研究費削減のため仕方なく
「闘魂BOOSTER」からコンデンサーを
外します。また作ればいいんです。
破壊無くして創造無しというか。
|
 |
そして、まだまだナマクラ知識を
承知で色んな形のコンデンサー
付けてみちゃったりします。
|
 |
基盤一応完成の図です。
|
 |
そして今回、満を持しての登場となる
アライさんの「ゴッドハンド」です。
ケースの穴あけと、華麗なグルーガン捌きで
LEDを取り付けてもらいました。
流石に私より上手いです。
手先の器用さには定評がありますからね。
|
 |
力仕事をヘルプしてもらったので
私の余力も充分です。
チャチャッと基盤装着及び内部配線を済ませ |
 |
スイッチオン。
緑一色一発ツモです。
16000オール・・・かと思いきや・・・
あからさまに出音が不安定です。
原因は半田付け不良と睨み
|
 |
一番不安定な取り付け方をしていた
コンデンサーを付け直すことにしました。
と、その時閃きました。どうせ付け直すなら
影響の程は不明にしろソケットにして
違う数値のコンデンサー片っ端から
試してみようではないかと。
|
 |
「RR DISTORTION」において絶大な効果を
もたらしてくれた「青くて大きいコンデンサー」
だったのですが、今回はボツ。
内緒にしたくなるくらい意表をついた
数値の積層セラミックが
好みの音となりました。
|
 |
一応、1台目と違うところを要約します。
1.コンデンサーを変えた。
2.所によりコンデンサーの数値も変えた。
3.「DRIVE」を上げると高域も増すことに
気が付いたのでポットの
数値を変えバランスを整えた。
4.何本か太いワイヤーに変えてみた。
では「OLIVE DRIVE OFF(116kbMP3)」を
基準にし音を出してみます。
音源の 前半はストラトキャスターのリアPU
後半はフロントPUです。(以下共通) |
 |
OLIVE DRIVEセッティングは
左写真を参照してください。
「OLIVE DIVE ON 1(135kbMP3)」
まぁこんな感じです。
トーンポットの数値を変えましたので
一台目とは違いセンター位置から
調整する方法にしました。
|
 |
少しDRIVEを上げてみます。
「OLIVE DIVE ON 2(125kbMP3)」
これです。こんな感じの音を出すための
試行錯誤だったのです。
今まで製作した中で一番荒々しいと
思いませんか?
ついでにフロントPUとセンターPUミックスで
ギター側のヴォリュームコントロールを下げた
音のサンプルです。
前半が10で後半は4まで下げてます。
実験のためDRIVEを3時方向まで
上げてみました。
GuitarVo.10&4 Sound(155kbMP3)
これも許容範囲な音でしょう。 |
 |
そしてフルドライブなのですが・・・
「OLIVE DIVE ON 3(153kbMP3)」
どうしても線の細い音になってしまいます。
が、その分トーンを絞れば、かなり改善されることが後日判明しましたので
実戦投入することとしました。
|
 |
結果から申し上げると
「インターネット恐るべし」であります。
まぁ、爆弾作っちゃう中学生もいるわけですから、
エフェクターの一個くらい
たいした事無いのかもしれませんが・・・
しかし、私としては学ぶ事の多い作業でした。
徐々にではありますが「直感」が
当たるようになってきました。
ヒョッとするとヒョッとするかも知れませんので、
まだまだ、エフェクター製作続けちゃうのであります。
OLIVE DRIVE SAMPLE(235kbMP3) |
| 少しだけ親離れ編 なんでもKO事務所LIVE |